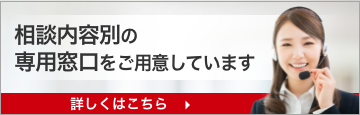トイレが長い社員に対して会社側が取れる対策とは?
- 労働問題
- トイレ
- 長い
- 社員

仕事中にトイレに行くのは、生理現象としてやむを得ない行動ですが、トイレ休憩が異常に長い社員がいると、業務が停滞してしまったり、他の社員にも悪影響が及ぶ可能性があります。
このような場合には、減給や懲戒などを検討する経営者の方も多いと思いますが、適切な手続きを踏んで行わなければ、社員から処分の有効性を争われてしまうリスクもありますので注意が必要です。
今回は、トイレ休憩が長い社員に対して会社側が取れる対策について、ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスの弁護士が解説します。
1、社員のトイレを禁止することは公序良俗違反やハラスメントの可能性
トイレ休憩が長い社員がいると、さまざまな支障が生じます。そのような場合に、社員のトイレを禁止することはできるのでしょうか。
-
(1)トイレが長い社員がいることで生じる問題点
トイレ休憩が長い社員がいると、以下のような問題点が生じます。
① 業務効率の低下
トイレ休憩が長いということは、それだけ実際の労働時間が減ることになります。労働時間が減ると与えられた業務を時間内に処理することができず、業務効率が大幅に低下してしまいます。
所定労働時間内に処理できない仕事は、残業をして処理することになりますが、会社としては本来支払う必要がなかった残業代を負担しなければなりません。
② 他の社員のモチベーションの低下
トイレ休憩で長時間離席している社員と頑張って仕事をしている社員とで給料が変わらないのであれば、頑張って仕事をしている社員が不満を抱き、仕事へのモチベーションが低下してしまいます。
社員同士の関係性も悪化し、職場環境悪化の一因となることもあります。 -
(2)トイレの禁止は公序良俗違反やハラスメントの可能性がある
上記のような支障を回避するために、トイレ休憩の長い社員に対して、トイレの禁止を命じることを検討している会社もあるかもしれません。
しかし、トイレに行くというのは人間の生理現象としてやむを得ないものですので、そのような行為を禁止するのは、違法な業務命令として、公序良俗違反となる可能性があります。また、特定の社員だけを対象にトイレの禁止を命じるのは、ハラスメントに該当する可能性があり、対象の社員から損害賠償請求をされるリスクもあります。
そのため、トイレ休憩が長い社員がいたとしても、トイレを禁止するのは現実的ではありません。
2、トイレでサボっているならペナルティの対象になる
トイレが長い社員が、トイレ内で仕事をサボっているのであれば、ペナルティの対象になります。
-
(1)社員には職務専念義務がある
社員には、労働契約上の義務として「職務専念義務」が課されています。職務専念義務とは、使用者の指揮命令に従い、職務に専念する義務のことをいい、簡単にいうと仕事中は業務に集中して、私的な行為は控えるということです。
仕事中にトイレに行くこと自体は、生理現象としてやむを得ない行為ですので、職務専念義務に反することはありません。しかし、トイレを口実にして、トイレ内でスマートフォンをいじったり、ゲームをすることは、業務とは関係のない私的な行為ですので、職務専念義務に反するといえます。
このような職務専念義務違反があった場合には、対象の社員に対して、懲戒などのペナルティを課すことが可能です。 -
(2)ペナルティを課すにはサボっている証拠が必要
職務専念義務違反を理由にペナルティを課す際には、社員が仕事をサボっている証拠が必要になります。「トイレが長い」という理由だけでは、本当に用便のために時間がかかっていたり、体調不良のためトイレにこもっているということも考えられます。不当な処分といわれないためにも、十分な証拠を集めてから処分を行うことが大切です。
証拠といっても、トイレ内はプライベート空間ですので、監視カメラを付けたり、のぞいたりすることはできません。そこで、以下のような証拠によって、サボっていることを裏付けていきます。- 離席回数や時間の記録
- 離席理由の調査
- 体調不良であれば医師の診断書の提出
トイレ休憩の回数や時間は、人によって異なりますので、多少回数が多い、時間が長いという程度であれば、それを理由に処分するのは難しいかもしれません。しかし、通常必要な回数や時間を著しく超えている場合には、不合理なトイレ休憩といえますので、サボっているとみなしてペナルティを与えることも可能といえます。
3、従業員の「職務専念義務」と「ノーワーク・ノーペイの原則」
従業員のトイレ休憩が長いときは、トイレ休憩の時間を労働時間から控除することができるのでしょうか。以下では、従業員の職務専念義務とノーワーク・ノーペイの原則について説明します。
-
(1)ノーワーク・ノーペイの原則とは
ノーワーク・ノーペイの原則とは、労働者が「労務」の提供をしていないときは、使用者は、「賃金」の支払いをしなくてもよいという原則です。たとえば、遅刻や欠勤があった場合には、労働者は、その時間働いていませんので、ノーワーク・ノーペイの原則により、労働しなかった時間分の給料を控除することができます。
ただし、ノーワーク・ノーペイの原則には、2つの例外があります。
1つ目は、年次有給休暇です。労働者が休暇を取得した場合には無給が原則となりますが、年次有給休暇は、賃金が保障される休暇です。そのため、年次有給休暇を取得した労働者に対しては、仕事をしていなかったとしても、賃金の支払いを行わなければなりません。
2つ目は、会社都合による休業です。部品の調達ができず製造ラインがストップしたなど会社都合の理由で労働者を休ませた場合には、平均賃金の6割以上の賃金を支払わなければなりません。 -
(2)トイレ休憩を労働時間としてカウントしないことはできるのか?
トイレ休憩が長い社員がいたときは、不合理なトイレ休憩の時間をノーワーク・ノーペイの原則に従い、賃金から控除することも理論上は可能です。
ただし、労働時間とは仕事としての動作をしている時間だけでなく、指揮監督下にあって指示を受けたら業務に対応しなければならない時間も含みます。たとえば、夜勤で仮眠室にいる時間や、営業所で運送の依頼が来るまで待機しているような時間などです。
そして、トイレも職場で、携帯電話などの呼び出しには応じなければいけない状況からすると、通常は指揮監督下にあるといえ、労働時間から外すことは難しいです。
4、従業員へのペナルティは就業規則に明示すべき
従業員に対して、懲戒処分というペナルティを与える場合には、あらかじめ就業規則に懲戒の種類および懲戒の事由を定めておく必要があります。労働者が企業秩序に違反する行為をすれば、当然に懲戒処分ができるとお考えの経営者の方もいますが、懲戒処分は、労働契約から当然に発生するものではありませんので、就業規則などで明示することが必要です。
トイレ休憩が長い社員がいる場合には、「正当な理由なく離席を繰り返すこと」などを懲戒事由として定めておくことで、対象社員への懲戒処分が可能になります。
ただし、就業規則に定めがあったとしても、対象社員を懲戒処分とする際には、懲戒事由に該当する事情を裏付ける証拠が必要になります。十分な証拠がない状態で懲戒処分を行ってしまうと、懲戒処分の有効性を争って訴訟提起されるリスクが生じますので注意が必要です。また、実際に懲戒を行う際は、手段として相当でなければならず、いきなり重い手段を取るには、それ相応の事情が必要になります(労働契約法15条)。
5、職務怠慢な従業員への対応は弁護士に相談
職務怠慢な従業員への対応でお困りの経営者の方は、まずは、弁護士にご相談ください。
-
(1)会社としての適切な対応をアドバイスできる
職務怠慢な従業員がいたとしても、すぐにペナルティを与えるのは避けた方がよいでしょう。何らかのペナルティを与えるには、正当な根拠に基づいて行う必要がありますので、就業規則などのペナルティが明示されているか、ペナルティが与えられることが従業員に周知されているか、職務怠慢を裏付ける証拠があるかなど慎重に判断する必要があります。
会社としてどのような対応ができるのかは、専門家である弁護士に判断してもらうのが安心ですので、まずは、弁護士に相談し、適切な対応をアドバイスしてもらうとよいでしょう。 -
(2)会社に代わって従業員対応を行うことができる
職務怠慢な従業員に対して、正当な根拠に基づきペナルティを与えたとしても、不満を抱いた従業員から「処分は無効だ」などと言いがかりをつけられる可能性もあります。
このような従業員とのトラブルが生じた場合には、弁護士に対応をお任せください。労働問題に詳しい弁護士であれば、労働者対応も慣れていますので、法的観点から会社による処分が正当なものであったことを伝えることで、納得が得られる可能性があります。
また、従業員の納得が得られず、裁判になった場合でも、訴訟対応を弁護士に任せることができますので安心です。
6、まとめ
トイレ休憩やタバコ休憩が長い社員がいると、業務効率が低下し、他の社員のモチベーションも低下してしまいますので、会社としては、早期に適切な対応をとる必要があります。
しかし、トイレ休憩自体は、生理現象としてやむを得ないものですので、トイレ休憩自体を禁止することは公序良俗違反やハラスメントに該当するおそれもあります。また、サボりを理由にその時間を賃金から控除する際にも、正当なトイレ休憩と区別して行わなければなりません。
このように、トイレが長い社員に対する処分を考えるにあたっては、さまざまな事情を考慮する必要がありますので、まずは、ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています