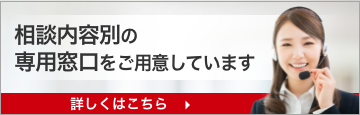【企業向け】会社都合で早退させたときの給与(賃金)の考え方
- 労働問題
- 会社都合
- 早退

足立区の労働基準監督署によれば、令和3年の賃金不払いに関する労働基準法違反の申告受理件数は101件ありました。
仕事量の減少や会社の経営難などの事情で、会社側から従業員に対して早退を申し入れて、休業を検討せざるを得ない場合もあるでしょう。会社都合で従業員を早退させることになった場合、どの程度の賃金を支払えばいいのか不安がある企業担当者もいらっしゃると思います。
本コラムでは、会社都合で従業員を早退させた場合における給与(賃金)の考え方などについて、ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスの弁護士が解説します。
1、会社都合で早退させた場合の賃金の考え方
会社の都合によって、従業員が定時よりも早く仕事を切り上げる場合に、その分従業員は労働を提供していないことになりますが、会社は賃金を支払う必要があるのでしょうか。
結論として、会社は賃金(休業手当)を支払わなければならない場合があります。具体的にどのようなケースで支払う必要があるのか、解説します。
-
(1)ノーワーク・ノーペイの原則
通常、会社は労働者に対して、労働の対価として賃金を支払う必要があります。言い換えれば、労働者が労働をしていなければ、賃金を支払わなくてもよいことになります。
たとえば、労働者が寝坊などによって1時間遅刻をしてきた場合、その1時間分について会社は賃金を支払う必要はありません。これをノーワーク・ノーペイの原則といいます。
しかし、労働者の都合ではなく、会社都合で休業させた場合も労働者に対して賃金を支払わなくてもよいとなると、労働者の生活が立ち行かなくなってしまいます。そこで、労働基準法第26条によって労働者の保護が図られています。 -
(2)休業手当を支払うことになる場合
労働基準法第26条では、使用者の都合によって労働者が休業した場合、使用者は労働者に対して、その平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない、と定めています。つまり、使用者の都合による休業の場合は、労働者に休業手当を支払う必要があるということです。
違反した場合は、30万円以下の罰金(労働基準法第120条第1項)や付加金(労働基準法第114条)の罰則があるため、注意が必要です。
また、労働基準法第26条は「強行法規」とされているので、たとえ労使間で休業手当を支払わないと合意をしたり、就業規則で、平均賃金の60%未満の休業手当を支払うと規定していたりしても無効です。会社は休業手当を60%以上は支払わなくてはなりません。
なお、民法上の規定によれば、使用者の責めに帰すべき事由によって働くことができなくなった場合には、労働者は、賃金の全額を受ける権利があるとされています。労働基準法は労働者の最低限度の生活保障を目的として、強行法規として賃金の支払いを保障していますが、これは民法の適用を排除する趣旨ではなく、競合する関係にあります。
しかし、後述するように、民法上の規定のほうが、使用者の責めに帰すべき事由を狭く解していることから、民法上の義務はなくとも、労働基準法を根拠に、休業手当を支払う必要が生じる場合もあります。
2、「休業手当」とは?
あらためて休業手当について解説します。
-
(1)休業手当も賃金
休業手当は「手当」とありますが、労働基準法においては、賃金として扱われます。したがって、通常の賃金の支払日に支払う必要があります。
-
(2)休業手当の対象者
休業手当を支払う対象となるのは、使用者と労働契約を締結した労働者です。雇用形態は関係なく対象になるので、パートタイム勤務やアルバイトの労働者も対象です。
-
(3)休業手当の支払額の考え方
休業手当は、働くことができなかった労働時間に対して60%以上支払うものではなく、1日の平均賃金に対して、60%以上を支払えば足りると考えられています。
たとえば、所定労働時間が9時から17時30分までの労働者が、会社都合で17時に早退することになったとします。この場合、9時から17時まで業務に従事したことに対して支払われる賃金は、1日の平均賃金の60%を通常は超えるでしょう。そのため、休業手当を支払う必要はありません。
しかし、会社都合で9時から11時までしか働けなかったような場合は、支払われる賃金が1日の平均賃金の60%に満たない可能性があります。この場合は、差額分を支払う必要が生じます。
なお、休業手当は「平均賃金×60%以上×休業日数」で算出することができます。
3、「会社都合」の考え方|休業手当の支払いが必要なケース・必要ではないケース
では、会社都合とは、具体的にどのようなケースが該当するのでしょうか。
-
(1)「使用者の責めに帰すべき事由がある場合」とは
休業手当の根拠となる労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合に、休業手当を支払わなくてはならないと規定されています。
「使用者の責に帰すべき事由」とは、会社側の故意または過失だけではなく、さらに広く会社側に起因する経営、管理上の障害も含まれます。このように広く解釈しているのは、労働者の生活保障を図る趣旨によるものです。
しかし、不可抗力によってやむなく休業せざるを得ない場合には、休業手当を支払う必要はありません。
不可抗力について、行政の解釈では、①当該原因が事業の外部より発生した事故であること(法令を順守することによって生ずる休業も含まれる。)、②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてなお避けることのできない事故であること、これら2つの要件を満たす必要があると解されています。
不可抗力の例としては、地震や台風などの天災事変が挙げられます。そのため、地震などによる休業は会社都合にはならないので、休業手当の対象外となります。 -
(2)休業手当の支払いが必要なケース・必要ではないケースの具体例
基本的な考え方としては、前述のとおり、不可抗力以外の会社に起因する休業では休業手当を支払う義務が生じ、不可抗力による休業は支払い義務がないということになります。
① 支払いが必要なケース- 経営不振(仕事がない、商品が売れない、資金調達が困難)により生産調整などを行うケース
- 原材料不足で稼働できないケース
- 設備や機械の不備、欠陥などがあったケース
- 使用者による違法な解雇、業務停止などがあったケース
② 支払いが不要なケース
- 地震や台風などの天災によるケース
- 正当なロックアウトによって工場や事業所が閉鎖されたケース
4、休業手当と混同されがちな「休業補償」・「休業補償給付」
休業手当(労働基準法第26条)と似て非なるものとして「休業補償」「休業補償給付」があります。これらは、休業手当とはまったく別の制度ですが、混同しているケースがしばしば見受けられます。それぞれ、どのような制度であるのかを、正しく理解しておくことが大切です。
「休業補償」は、労働基準法第76条に根拠があり、業務上の災害が原因で労働者が労働を行えない場合に、平均賃金の60%を会社が休業補償として支払うものです。
この休業補償は業務災害から3日目までは会社が支払うもので、4日目以降は、労働基準監督署(厚生労働省)が労災保険として支払う「休業補償給付」に移ります。「休業補償給付」は労働者災害補償保険法に基づく保険給付です。
このように、「休業手当」と「休業補償」「休業補償給付」は制度が異なるものです。大きく異なるのは、支払いの原因が、「休業手当」だと、使用者の責めに帰すべき事由によるのに対し、「休業補償」「休業補償給付」の場合は、業務上の怪我や病気によるものである点です。
他にも、支払い元が異なるほか、「休業手当」は平均賃金の60%以上であったのに対して、「休業補償」「休業補償給付」は平均賃金の60%(休業特別給付金を含めると、平均賃金の80%)となり支給額が異なります。また、「休業手当」は賃金であることから、課税対象になりますが、「休業給付」や「休業補償給付」は非課税であることなども大きな違いといえるでしょう。
5、まとめ
会社都合で従業員に早退をさせたような場合には休業手当を支払う必要がありますが、具体的なケースで会社都合として休業手当を支払う必要があるかどうかは、頭を悩ますことが少なくありません。また、近年は新型コロナウイルスの影響もあり、判断が難しい事例もあります。
休業手当を含め、労務問題にお悩みの企業経営者・担当者の方はベリーベスト法律事務所 北千住オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています